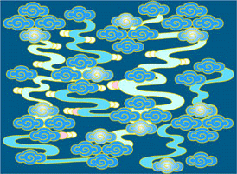
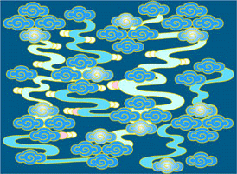
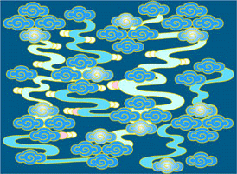
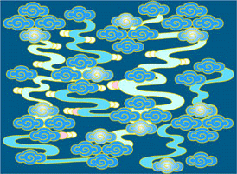
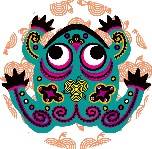
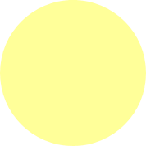
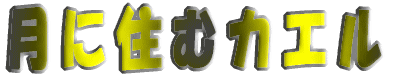
天の女神は納西の祖先に三百六十種の卜占の本を与えることにした。
本を箱に入れ、使者のコウモリに途中で開けてはならないと言いつけて持たせた。
ところがコウモリは途中で箱を開けてしまったから、聖書は風邪に吹かれて飛び散った。
最も重要な本は黄金の大蛙が飲み込んだ。
コウモリは弓の名人として知られる蛙神三兄弟のところに行って、大蛙を射てほしいと頼んだ。
三兄弟が大蛙を射ると、蛙は「私は頭を南、尾を北、体を東、腹を西に向けて死ぬ。」と言い残して死んだ。
こうして東には木が、南(蛙の口)からは火が、西(の蛙の骨)からは鉄が、北(の胆)からは水が、
そして蛙の肉からは天地中央の土が生じた。
ここから五行が発生し、これを青蛙五行と呼ぶ。
雲南省麗江の納西族の神話より
大昔、宇宙は真っ暗闇だった。天と地はくっつき、万物も光も色も音も、何ひとつ無かった。
後になって、宇宙に天神木比塔(ムピタ)が現れた。
一人で寂しくて大泣きに泣くと、その涙は宇宙を満たしていった。
それからまた長い時間が経って、涙の水から気が生じ、その気は雲と蛙に変じた。
それから天神は九ひらの雲で天を造り、蛙の皮で大地を造った。
蛙皮は反り返ろうとするので、棒で叩いた。
皮はそれでもこちらを伏せたと思えばあちらで反り返るので、棒切れで切っていった。
こうして大地に平地や山谷ができ、何もしなかったところは高山になった。
羌(チャン)族の神話より
この月に蛙がいるという思想は太陽に烏がいる思想と共に日本に入ってきており、
天皇の即位式に紫宸殿前を飾る“月像幢”には兎と共に描かれた蛙がいます。
正倉院宝物の弦楽器“桑木阮咸”の腹板には、臼を搗いている兎と蛙の絵が描かれています。
京都の仁和寺の「別尊雑記」には、三足の烏がいる太陽と、兎とヒキガエルのいる月を両手に
かざし持つ、北極星を神格化した妙見菩薩(中国では北斗真君)を中心し据えた別尊曼荼羅が
記されています。
中国の少数民族にも様々な蛙の伝説が宇宙規模で語られています。
中国では月に蛙が住んでいるという伝承があり、前漢の「淮南子」や東晋の「捜神記」、
南朝宋の「後漢書」にも記載されています。
前漢時代の馬王堆第一号前漢墓の帛画には天上界の弓張り月に蛙が描かれていますし、
やはり漢代の郭氏墓石祠の石刻天象図には太陽に住む烏と月住む蛙が共に描かれています。
百田弥栄子の「中国の伝承曼荼羅」に詳しく書いてありますので、御紹介します。
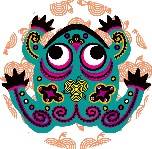
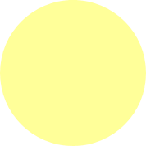
日本では蛙はゲロゲロ鳴くイメージですが、
中国少数民族地帯の蛙はルルルルーッと高く澄んだ声で鳴き、
壮(チワン)族では蛙を雷神の娘の天女と見なすそうです。
宇宙の始め、この世は果てのない大海原で、海面を一匹の金色の蛙が漂っていた。
天神が地球を造ろうと思って土を一つまみ蛙の背に置くと、蛙は水底へ沈んで行く。
天神はあわてて弓矢をとって蛙を射ると、蛙は浮き上がって来た。
天神は再び一つまみの土を背に置くと、蛙はくるりと返ってその土を抱いた。
こうして地球は金色の蛙の懐で形成されていった。
土(トゥ)族の伝承「地球の形成」より
更に、天地創造が蛙によって成されたという神話まであります。
張果老が天を造った頃、地上には水が多すぎた。そこで張果老は二十四の太陽を造って、昼夜地上を照らさせた。
蛙は怒り、地上にただ一本残っていた馬桑樹に登ると、二十二個の太陽を次々に呑み込んだ。
残りの二個を呑もうとした時、観音菩薩に見つかった。怒った観音は棒で馬桑樹を打ち据えたので、馬桑樹は背の低い
曲がりくねった木になってしまい、蛙はもう太陽を呑むことができなくなった。
観音は太陽に、一個は昼に出て地上を照らすように、もう一個は夜出て地上を照らすようにと命じた。
土家(トウチャ)族の「天地を造った張果老と李果の神話」より
天宮にいる金色の蛙が月を見初めたが、兄の太陽を恐れて、月が顔を隠す暗い夜に月に近付いた。
雲南省のタイ族 「月食の伝説」より
(弓の名人)羿(げい)は西王母に不死の薬を願って手に入れたが、妻の恒我(常我ともいう)がそれを盗んで月に奔り、
月に身を寄せて蟾蜍(ヒキガエル)となった。月の精となったのである。
「淮南子」より
月の黒い影は蛙が踏んだ時にできた爪の痕 雲南省のラフ族の神話的叙事詩「牡帕密帕」より